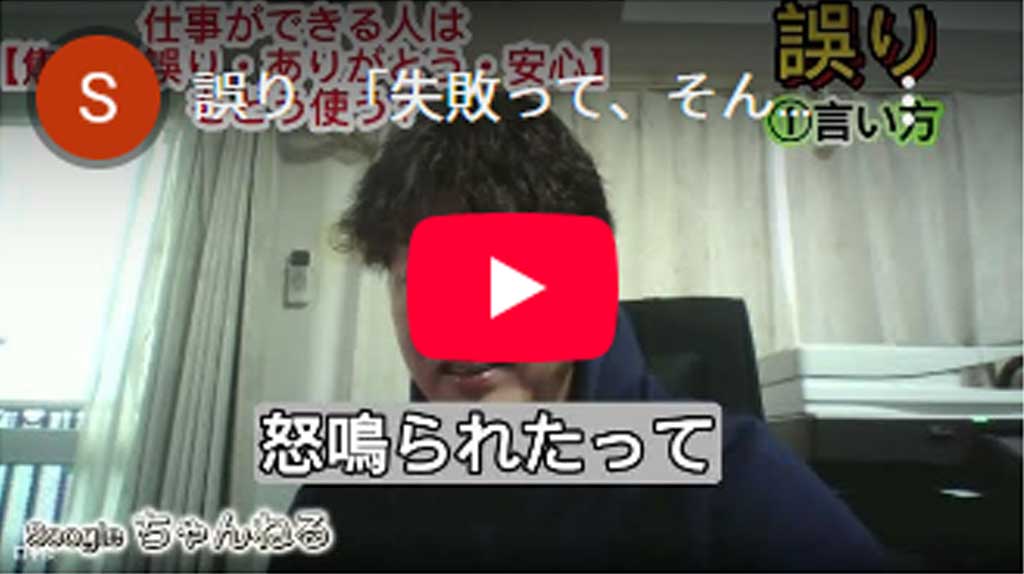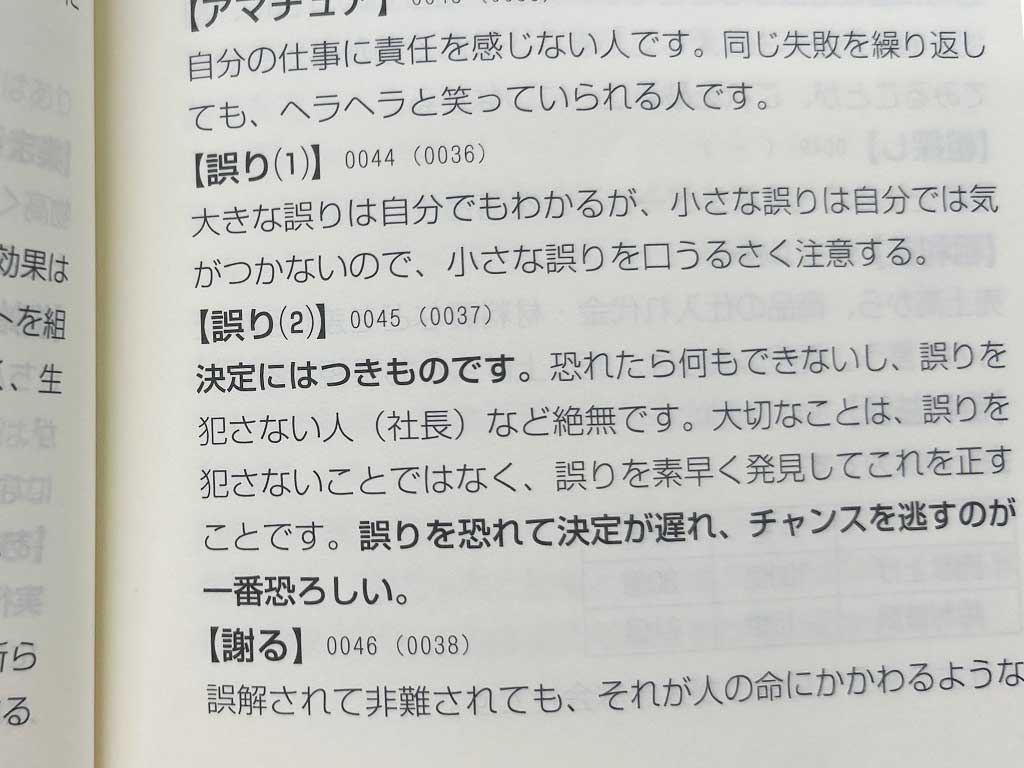
私たちは日々の仕事の中で、大なり小なり「誤り(ミス)」に直面します。
大きな失敗には気づけても、意外と自分では気づけないのが“小さな誤り”。
ですが、この小さな誤りこそが、
「成長のチャンス」であり、「信頼を積み重ねる場面」であり、「チームの未来を左右する分岐点」にもなります。
今回の勉強会では、そんな「誤り」とどう向き合い、どうチームで乗り越えていくかをみんなで考えました。
【誤り】=成長のきっかけと捉える
「大きな誤りは自分で気づける。でも、小さな誤りは自分では気づけない。」
これは仕事だけでなく、人との関わりや日常のあらゆる場面でも当てはまります。だからこそ私たちは、お互いに小さな誤りにも気づき合い、伝え合うことが必要です。
特にお店の現場では、「その場で」「すぐに」「丁寧に」伝えることが大事。小さなミスを放置すると、やがて大きなトラブルへとつながります。
ミスを責めるより、共有する文化を
私たちの会社では、失敗したこと自体を責めることはしません。大事なのはその後。
- なぜ失敗が起きたのか?(原因)
- 次に同じことが起きないためにはどうするか?(対策)
- 他の店舗でも起きないよう、どう共有するか?(水平展開)
これが失敗の価値を最大化するという考え方です。
ミスを隠したり、報告しなかったりすることが一番の問題。なぜなら、他店舗でも同じことが起きてしまう可能性があるからです。
「できない」ことはその人の個性
同じミスを繰り返すスタッフに対して、
「なんで何回言ってもできないんだ」と思ってしまうこと、ありますよね。
でも、ここで大事なのは【その人の苦手】を理解すること。
人には向き不向きがあります。
苦手なことに何度もチャレンジして、それでも少しでもできるようになったら、その時はしっかり褒めてあげれば良いんです。
それがチームで働くということです。
リーダーの伝え方が、店の空気を変える
忙しい時にイライラして、強い言い方をしてしまったことは誰しも経験があるはず。でも、大事なのは伝え方。
- 「バカじゃないの?」ではなく「どうすれば次できるか、一緒に考えよう」
- 「なんでできないの?」ではなく「ここが苦手なのかもしれないね」
失敗に対して冷静に対応することで、店舗全体の雰囲気が良くなり、結果的にお客さまにも良いサービスが提供できます。
共有することで、他店舗も守られる
たとえば千葉ニュータウン店で起きたクレームは、君津店や8000代店でも起きる可能性があります。
だから、ミスやクレームは店舗内で終わらせず、全店に展開して共有する文化をつくっていきます。
それが全体のレベルアップにつながるからです。

「ミスをしないように生きる」のではなく、「ミスをしても、そこから素早く学ぶ」こと。
それが、強い個人と強い組織を作る一番の近道です。完璧じゃなくていい。でも、改善を止めない。
この姿勢を、チーム全体で大切にしていきましょう。
気づきのレシピはYouTubeでもご紹介していますので、ぜひご覧ください。