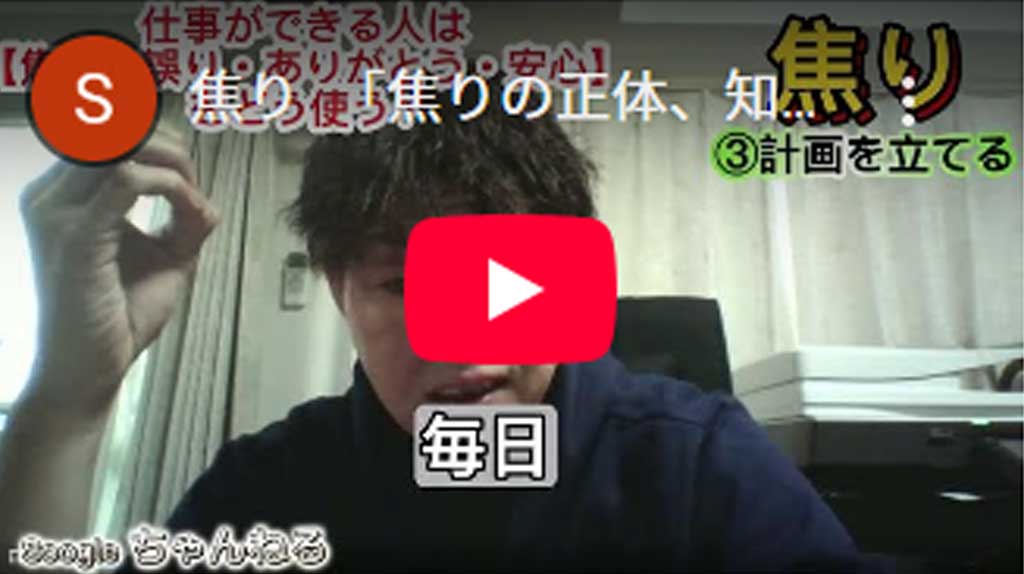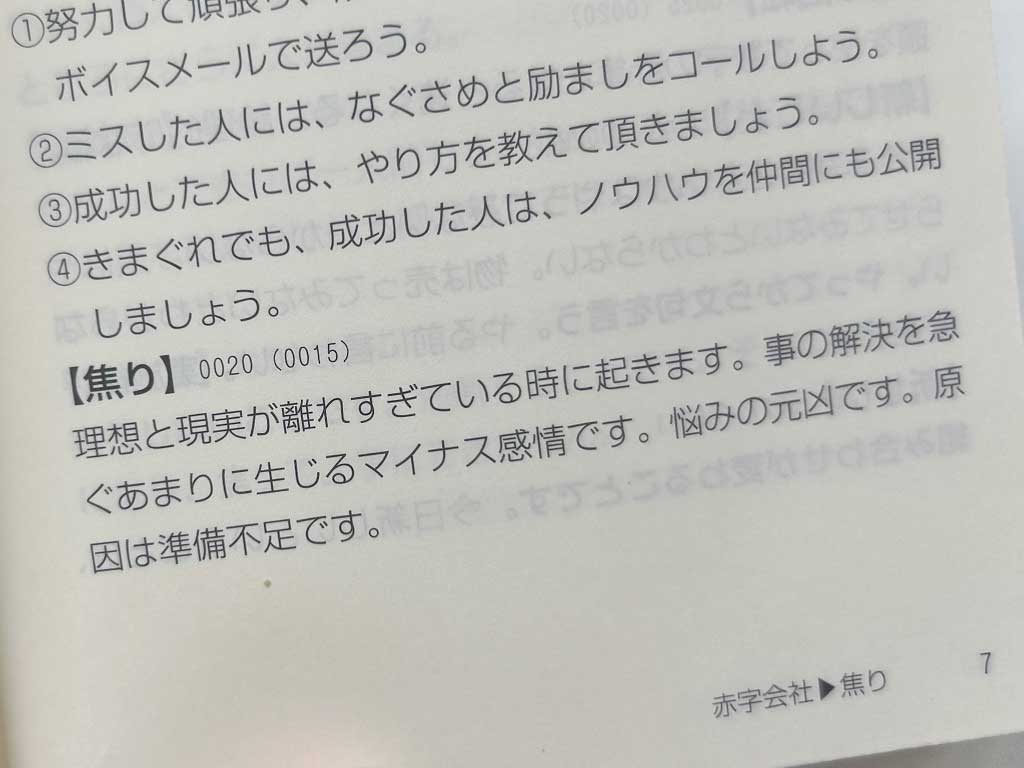
日々の仕事の中で、誰しも「焦り」を感じる瞬間があります。
理想と現実のギャップに直面したとき、
「時間がない」「準備が追いつかない」「どうしよう…」という思いが頭をよぎります。
焦りは、悪者のように扱われがちですが、実はそれ自体が問題なのではありません。
真に問題なのは、焦りを生む準備不足にあります。
準備が不十分なまま動き出せば、焦りはすぐに不安やミスへと連鎖してしまいます。
今回の勉強会では、「焦りとは何か」「なぜ焦るのか」「どうすれば焦りを乗り越えられるか」をテーマに、現場の視点から考えました。
焦りは、準備不足が生むマイナス感情
焦りとは、理想と現実のギャップから生まれるマイナス感情です。
「こうなってほしい」「こうあるべきだ」と考える理想に対して、現実がついてこないとき、人は不安になり、焦りを感じます。
たとえば、「予約が入っていたのに管理ができていなかった」「イメージしていた状況と違った」「段取りが足りず、作業が追いつかない」――こういったケースでは、焦りが一気に生まれます。
しかし、焦りそのものが悪いのではありません。
焦りの“本当の原因”は、準備不足にあるのです。
つまり、焦りは「準備が足りていなかった」と教えてくれる、ひとつのサイン。
だからこそ、焦ってから慌てて行動するのではなく、焦りを感じる前に、どれだけ準備ができていたかが大切です。
日々の仕事において、段取りをしっかり整え、先を見越して動いていると、自然と焦る場面は減っていきます。
逆に、準備を怠れば、どんな場面でも「どうしよう…」と気持ちが乱れてしまいます。
焦りを防ぐ第一歩は、日常業務の「見える化」と「計画性」です。
「備えあれば憂いなし」、まさにその言葉通り、準備は私たちの心の余裕にもつながっています。
準備=段取り 8割の力で焦りを制す
- イメージする力を働かせて、あらゆる可能性を想定して準備を進める
- 仕込み表・発注スケジュールなど、普段から使うツールをしっかり活用
- たとえば「木曜日に仕込み→月曜の在庫を見つつ調整」「発注をいつまでに出すか」など、先読みして動く
- 段取り・準備を8割完成できていれば、突然の変化にも焦らず対応できる
「段取り8分、仕事2分」という言葉があります。
この意味は、準備に時間をかければかけるほど、本番では慌てず確実に動ける、ということです。
焦りを感じたらどうするか? ~対処と習慣~
- 焦りの原因を探る
何が準備できていなかったか?
情報・段取り・人員・器具など、どこにズレがあったかを振り返る。 - 次に備える対策を打つ
同じような場面が来たらどう動くか、あらかじめパターンを想定しておく。
例えば、突然の来店、予約の重複、注文変更など。 - 共有と水平展開
ニュータウンで起きた事例を他店舗にも伝える。
「君津でも同じことが起こるかもしれない」意識を持つ。 - 日常の積み重ねが強さをつくる
段取り・準備の習慣を徹底することで、多少の変化は想定内になる。
準備を怠らず、小さなズレを放置しないことが肝要。

焦りをただ抑え込もうとすれば、感情に振り回されてしまいます。
ですが、焦りの根本にある準備不足に目を向け、対策を打っていけば、焦りはむしろ味方になります。
理想と現実が離れるときこそ、
一歩先を見据えた段取りと準備が、仕事の質を高め、安心感を生み出します。
今日のテーマは「焦り」。
焦りを恐れず、準備で制するチームであり続けましょう。
気づきのレシピはYouTubeでもご紹介していますので、ぜひご覧ください。